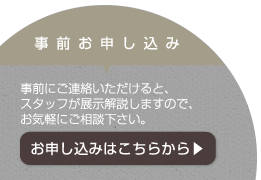読み込み中...
読み込み中...月イチガク⑤「墓場放浪記 ~墓と石の旅路を追って~」
–
古い墓石は地域の歴史を物語ります。
時代によって形が移り変わり、使われる石材は地域の文化圏を反映し、大きさや作りが弔われる人の力を反映する。そして、長い時間、その場所にとどまる。
最近、墓石に注目して記録に残っていない地域史を解き明かそうという試みが島根県各地で行われています。
その先駆的存在である、考古学の手法で墓石を研究する間野大丞さん(島根県教育委員会)と中村唯史の対談で、石材の産地とその流通から見える歴史に迫ります。
オンライン参加(予約不要) ご希望の方は下のリンクからZoomにアクセスしてください。
https://us02web.zoom.us/j/3427450025?pwd=WVZIcVV5bGMvSENJM3dDck1ZeUpxUT09
ミーティングID: 342 745 0025
パスコード: azukihara
月イチガク⑥「気候が変? どう? ~気候変動の過去未来~」
–
今、気候に何が起きていて、これからどうなるのでしょう。
気候の未来を予測するには、過去の気候変化を知ることが欠かせないとされ、近年は年輪を用いた高精度での古気候解析が行われています。
地質時代の古気候や現在の気候を紹介しながら、将来についてエコサポしまねの葭矢崇司さんと一緒に考えます。
オンライン参加(予約不要) ご希望の方は下のリンクからZoomにアクセスしてください。
https://us02web.zoom.us/j/3427450025?pwd=WVZIcVV5bGMvSENJM3dDck1ZeUpxUT09
ミーティングID: 342 745 0025
パスコード: azukihara
月イチガク⑦「大田の海から続く道 ~ワニ、塩鯖そしてワカメの旅路~」
–
三次名物「ワニ料理」のルーツは大田にあり。
かつて大田の沿岸で採れた海産物は、中国山地の山間部に流通しました。サメ(ワニ)や塩鯖、ワカメなどがどのような道で運ばれたのでしょう。そこには石見銀山からつながる街道が関係していたかも知れません。
また、三次でワニ料理が名物になっているように、今の文化に当時の名残をみることができるのでしょうか。
海と道に焦点をあてたお話を、多田房明さん(山陰民俗学会)にうかがいます。
オンライン参加(予約不要) ご希望の方は下のリンクからZoomにアクセスしてください。
https://us02web.zoom.us/j/3427450025?pwd=WVZIcVV5bGMvSENJM3dDck1ZeUpxUT09
ミーティングID: 342 745 0025
パスコード: azukihara
月イチガク⑧「地図がオモシロイ ~地理屋と地質屋が地図を読む~」
–
地理の目線で地域の面白さを生徒に伝える阿部志朗さん(大田高校)と地学で地域をみる中村唯史(縄文の森)の対談で、地理院地図や古地図から読み解くことができる大田市地域の歴史や大地の成り立ちを紹介します。
2024年春に完成したばかりの大田市の高精細「赤色立体図」も紹介予定です。
オンライン参加(予約不要) ご希望の方は下のリンクからZoomにアクセスしてください。
https://us02web.zoom.us/j/3427450025?pwd=WVZIcVV5bGMvSENJM3dDck1ZeUpxUT09
ミーティングID: 342 745 0025
パスコード: azukihara
月イチガク⑨「縄文の宝島『隠岐』 ~大地と人の2万年~」
–
黒くきらめく黒曜石は縄文の宝。
貴重な宝の石を産出する隠岐を目指して、縄文人は丸木舟で海へこぎ出しました。
人々が2万年近くにわたって隠岐の黒曜石を目指す間に大地は大きく変化した歴史があります。
その後、隠岐は遠流の島としての時代、北前船の中継地としての時代を経てきました。
現代に至るまで、人々の暮らしに影響し続けている隠岐。
チガク的視点で、「遠くて近い島」の大地と海と人に注目します。
オンライン参加(予約不要) ご希望の方は下のリンクからZoomにアクセスしてください。
https://us02web.zoom.us/j/3427450025?pwd=WVZIcVV5bGMvSENJM3dDck1ZeUpxUT09
ミーティングID: 342 745 0025
パスコード: azukihara
月イチガク⑩「東洋一の金鉱山・瑞芳 ~藤田組が手がけた鉱山~」
–
「千と千尋の神隠し」の舞台と噂されるようになってから、日本をはじめアジア各国から多くの観光客が訪れる台湾の九份。
この町は、近代に佐渡金山をしのぐ、アジア最大の金鉱山の町として成立しました。
明治時代に九份の開発に乗り出したのは、大森鉱山(石見銀山)を経営していた藤田組です。鉱区を分けて東側の金瓜石は釜石製鉄所などを経営した田中組で、九份と金瓜石は当時の面影を色濃く残します。
この回では、瑞芳鉱山(九份、金瓜石)の歴史と今の風景を紹介します。
オンライン参加(予約不要) 希望の方は下のリンクからZoomにアクセスしてください。
https://us02web.zoom.us/j/3427450025?pwd=WVZIcVV5bGMvSENJM3dDck1ZeUpxUT09
ミーティングID: 342 745 0025
パスコード: azukihara
月イチガク⑪「超レアなアナ ~松江のアナ・大田のアナ~」
–
松江市の大根島にある溶岩隧道は、本州ではここと富士山麓でしかみることができない希少な地形。
そのガイドを務めている松原慶子さん(出雲国ジオガイドの会)に、竜渓洞の面白さを紹介していただくとともに、島根半島の潜戸や洞窟遺跡、大田市にある数々の興味深い穴について、中村唯史(縄文の森)との対談で紹介します。
オンライン参加(予約不要) ご希望の方は下のリンクからZoomにアクセスしてください。
https://us02web.zoom.us/j/3427450025?pwd=WVZIcVV5bGMvSENJM3dDck1ZeUpxUT09
ミーティングID: 342 745 0025
パスコード: azukihara
月イチガク⑫「“火山の谷”大田町を歩く」
–
大田の市街地は火山の谷に成立した??
大田町をぶらぶら歩きながら、三瓶火山の活動が地形に与えた影響と、町の成り立ちに関わりる地形を探ります。
町の各所で見ることができる三瓶火山の巨大噴火の痕跡、誰が名付けたか「トリス坂」と駅通り、町の景色がこれまでと違って見えるまちあるきです。